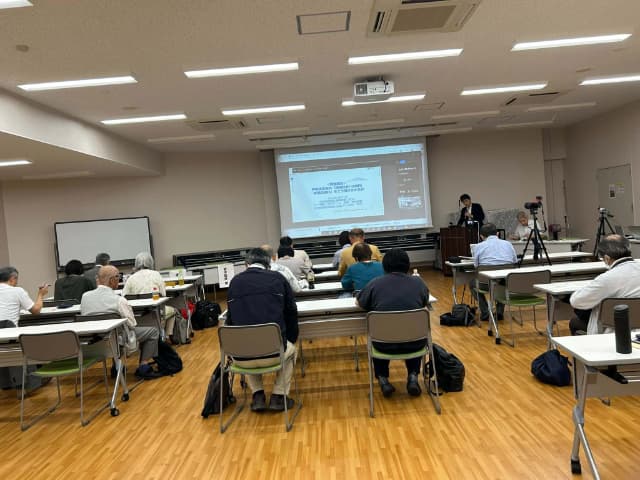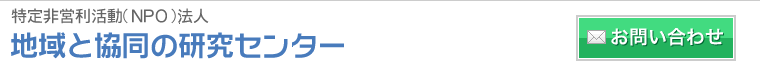【25.06.21】「協同組合のアイデンティティ」連続セミナー 第1回
「協同組合のアイデンティティ」連続セミナー 第1回 開催
「協同組合のアイデンティティ」連続セミナー 第1回
―― 協同組合は地域にどう関わるのか ――
6月21日、生協生活文化会館にて、「協同組合のアイデンティティ」連続セミナーの第1回を開催しました。
オンラインは約40名、会場には約20名が参加し、協同組合のアイディンティティをテーマに、実践と理念の両面から活発な議論が交わされました。
冒頭では、前田健喜氏(日本協同組合連携機構/JCA)による問題提起がされました。
協同組合声明改訂案に盛り込まれた「地域社会への関与・参画の強化」の背景や意義が語られ、協同組合が“社会変革の主体”として、どのように地域に向き合うべきかという本質的な問いが投げかけられました。
続いて、鈴木稔彦氏(生活協同組合コープみえ 理事長)より、地域福祉・行政との連携を軸とした協同組合の実践が報告されました。
「第7原則 コミュニティへの関与」をめぐって、協同組合が民主主義を育む現場であり、社会を変える主体であることの意味が語られました。報告の中で、鈴木氏は次のような言葉を印象的に共有しました。
・私たちは鎖で繋がれたロバなのか。 制約を越えて、社会を変えていく存在としての協同組合を考えたい
・折り鶴を折るような静かな営みが、平和な社会の土台になる。日常の中に協同組合の価値がある
・お金は成果を示す“指標”ではなく、“めぐり”としてとらえる発想が必要
休憩時間には、5月2日に滋賀県日野町で開催された「協同の縁 交流会 in 近江・日野」の取り組みを紹介する動画が上映され、地域に根ざした協同の実践の様子が共有されました。
後半は、JA関係者3名による実践報告が行われました。
廣田令寿氏(JAひだ/高山市)
多世代協働による「SUNSUN会」の取り組みを紹介。
加藤久美子氏(JA愛知東/新城市)
「やなマルシェ」、「つくしんぼうの会」「ドレミの会」、「地域ささえ愛組織」など、住民主体の助け合いの実践を紹介。
福田真由美氏(JAグリーン近江)[オンライン参加]
滋賀県日野町の「桜谷地域農村RMO推進協議会」による地域包括的な取り組みを報告。
※農村RMO(農村型地域運営組織)とは、複数の集落の機能を補完しながら、農用地の保全、農業を核とした経済活動、生活支援などを通じて地域コミュニティの維持・再生を目指す組織です。
JAの登壇者3名による報告の後、前田氏のコーディネートのもと、パネルディスカッションが行われました。話題は「共生」や「協働」といった協同の力の再確認から始まり、協同組合が地域の中で果たすべき役割、そして地域再構築に向けた方向性へと議論が展開されました。
なかでも焦点となったのは、地域課題の解決に取り組むことで、協同組合がどのように社会的役割を果たしていけるかという点でした。また、協同組合職員への期待として、「地域づくりを共に担う存在」や「地域住民の幸福度を高める担い手」としての意識と行動が求められていることが共有され、現場の視点と将来のビジョンが交差する活発な意見交換の場となりました。
その後、栗田暢之氏(認定NPO法人レスキューストックヤード 代表理事)より、「大規模自然災害と生協への期待」と題した報告が行われました。
阪神・淡路大震災以降の災害対応経験をもとに、協同組合が物資提供にとどまらず、平時からの“共助の仕組みづくり”や災害に強い地域社会の担い手となるべきことが提起されました。
セミナーの最後には、参加者を交えたディスカッションが行われました。テーマは「民主主義」「協同組合の役割」「職員の評価」など多岐にわたり、現場感のある率直な対話が展開されました。
民主主義の原則である「一人一票」については、単に多数決で物事を決めるということではなく、一人ひとりの声に耳を傾け、少数意見にも敬意を払うことこそが重要であり、声の大きさで物事が決まるのではなく、異なる考えを理解し合おうとする姿勢こそが、協同組合における民主主義の本質だという意見が共有されました。
また、協同組合職員の評価についても、「地域の人の暮らしが豊かになっているか」「笑顔が増えているか」といった視点で物事を捉える重要性は共有されつつも、現場ではその評価軸が制度として十分に定着していないことへの課題感が語られました。
「問題提起はできても、そこから次の行動へどうつなげるかが難しい」といった率直な悩みも共有されました。さらに、協同組合の社会的役割と制度的な位置づけについても触れられ、国会での「協同組合振興に関する決議」が紹介されるなど、政策面での注目の高まりも共有されました。
参加者からは、「協同組合のネットワークと“マインド”は、他のどのセクターにもない強み」であり、「人々の幸せをめざして、それぞれが歩んでいる」という共感が広がりました。
最後に、「同じ土俵で、一緒に話ができることこそが大切」というコメントもあり、協同組合が立場や肩書きを越えて対話を育む場であることの価値が再確認されました。